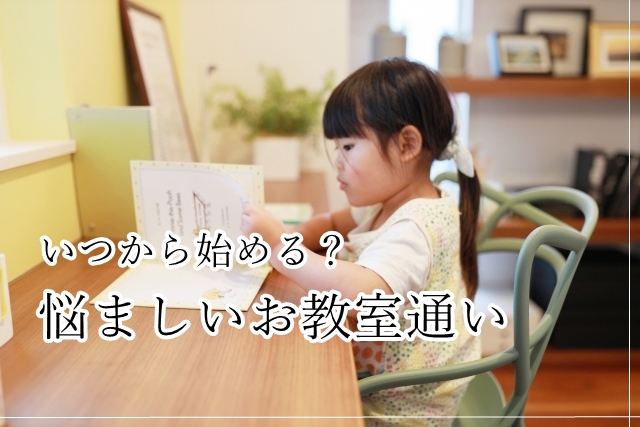小学校受験で親に求められること

まだ、小さい子どもがチャレンジする小学校お受験。
当日までに「準備を整えておく必要があること」は
沢山あるものの、
単に早く始めれば良いというわけでもないのが
小学校お受験でしょう。
そもそも本人には、受験の意思はまだありませんので、
概ね親の願いで進められていることも、
一つの大きな特徴です。
「いかに子どもの気持ちをのせていくか」がすべて
であり、「無理をさせずに」「頑張らせること」が必要です。
親に求められるのは「力量」です。
具体的には、
・子どもの気持ちになって考えること
・子どもを尊重すること
・見通しをたてて子どもの成長を捉えていくこと
・子どもの経験の質が高まる環境を整えること
・子どもの成長のプロセス意識すること
・正しい情報を収集すること
・子育ての信念を持つこと…
でしょうか。

中でも、「子育ての信念を持つこと」は
受験を考える上で、とても重要となってきます。
・どのような子どもに育って欲しいのか
・そのために、家庭ではどのような経験を重んじているのか
まずは、この基盤の部分を言語化してみましょう。
その上で、
・なぜ、受験をさせたいのか
・受験をすることで、どのような力を備えさせたいのか
・なぜ、その小学校に行かせたいのか
・その小学校の6年間で、どのような経験をさせたいのか
・親としてどのようなサポートができるのか、必要なのか
これらを考えていきます。
明確に自分なりの答えがあるなら、
もう心は「受験」に決まっているということですね。
まだ曖昧な場合には、
単なる憧れで進めて行く前に、
基盤の部分をしっかり整える必要があるでしょう。
「いつから始める?」を考える前に、
まずは自分の心と向き合う必要があるということです。
受験することは決まった!という方へ

この小学校に通わせたい!と明確な答えがある場合には、
お受験を目的とした教室選びがスタートです。
いつから始める?
「いつから始める?
に関しては、
どれだけの期間が準備のために必要なのか、
専門家の先生に相談されるのが一番良いでしょう。
お子さまの未来に向けて、
しっかりと両輪になれるお教室が見つかったら、
後は、丁寧にしっかりと、準備をしていくということになります。
その学びはお子さまのためになっている?
当然ですが、合格を目指した学びであっても、
その限りではない…、
つまり「合格だけを目的とした学びではない」ということ。
このことは意識する必要があります。
☑ お教室で学ぶことが、
今のお子さまにとってワクワクした経験となっていること
☑ お教室で頑張ることが、
将来のお子さまにとって大きな力となるであろうこと
この2点は、「受験の後
のことを考えても
とても重要なポイントとなります。
興味はあるものの、まだ決められない方へ
人生の選択肢も豊富になった今、
それでいて、教育の現場は大きな過渡期にある今、
小学校受験に対する興味はあるものの、
他の選択肢もあるので決められない…
このようなお考えの方が多くおいでになるのも事実です。
ここでは、受験をするかどうかはまだ決まっていないけれども、
「子どもの経験としての幼児教室
には興味があるという方に、
ぐるぐると回る思考を整理するための材料を
お示ししていきたいと思います。
いつから始める?

この問いに対する答えは、「いつからでも」。
幼児期の子どもの習い事の目的は、家庭によって様々です。
習い事の目的が明確であれば、得られるものが確実になるとともに、
子どもにとっても、より豊かな経験となることでしょう。
・〇〇の経験をさせたいから
・家庭ではできない教育をうけさせたいから
お教室通いをする理由を、
まずは言語化してみると良いですね。
次に考えるのは、
「うちの子は楽しめるか」ということ。
お教室通いの目的が明確であっても
肝心の本人が楽しめる状況でなければ、
良い結果にはなりません。
子どもにとって、「遊び」と「学び」には
境界線がありません。
没頭して遊んでいる時に
その遊びは深い学びとなるのです。
ですから、
・通いたいお教室の内容には興味がありそうか
(この先興味を持てそうか)
・楽しめるだけ子どもは成長しているか
(この先の成長が期待できるか)
まずは、このような観点で、
お子さまの状況を捉えてみることが大切です。
「準備ができている!
と感じるならば
2歳であっても3歳であっても
スタートするには早すぎないということになります。
逆に、5歳であっても、
そこに楽しめる環境がないのならば、
教室通いを優先するより
お子さまがどのようなことに興味を持っているかを
探ってみることからはじめてみると良いでしょう。
どちらを選ぶ?幼児教室2つのパターン

次に、どんな角度で教室を選ぶのかについて考えていきましょう。
習い事にはいろいろありますが、
幼児教室となった場合、
大きく2つのパターンに分けられるのではないかと感じます。
☑「合格に向けた学びを展開するお教室」
と、
☑「今必要なこと、今楽しめることを行っていくお教室」
です。
前者は合格というゴールに向かって
段階的に必要なことを展開していくお教室であり、
後者は、今楽しめることを積み上げていくお教室というイメージです。
もちろん、後に受験につなげていくことも可能です。
実際行う内容には
さほど違いはないのかもしれませんが、
ゴールが明確にある場合には、恐らく前者の方が
より着実に進んでいけると思いますし、
この先の子どもの様子を見ながらゴールを決めていくという場合には
後者の方がゆったりと今を楽しみながら
進めていくことができそうです。
ご家庭の方針に応じて、
そして、お子さまの様子を観察しながら、
いずれのパターンのお教室が今はあっているかを
決めていけるといいですね。
「孤育て」からの脱却

かつての日本社会では、
子育ては地域全体で行っていくものでした。
今はというと…
地域とのつながりは希薄になり、
祖父母さえも仕事に忙しくサポートが難しい状況かもしれません。
気づけば子育てを一人で行っている…。
「孤育て」
を強いられ、
そこから大きなストレスを抱える保護者さまが多いことも現実です。
もちろん子どもの育ちは親に責任があるのですが、
子育ては一人でおこなう営みではありません。
繋がれる人を探して、
所属できるコミュニティを見つけて、
「みんなで子育て」に是非向かって頂きたいと思います。
特に受験という大きなハードルを超える際には、
親も子も気持ちのコントロールが難しいもの…。
「孤育て」から脱却し、誰かに相談する勇気を持ってくださいね。
皆で未来の担い手である子どもの育ちを応援していきましょう。