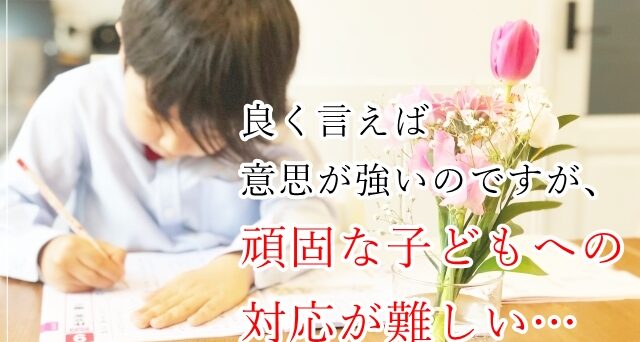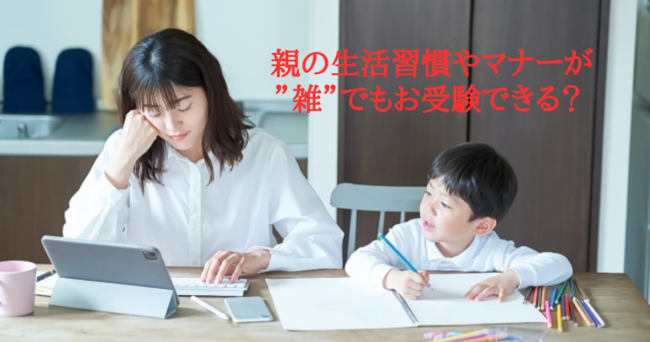新しい環境に慣れるのに時間がかかり、イライラしてしまいます…
その言葉は逆効果!子どもの心まで傷つけてしまいます

元気いっぱい遊んでいる子どもって
見ていても微笑ましいですし、
子どもらしい…と感じますよね。
どうも私たちは無意識のうちに
「子どもらしさ」を勝手に定義しているようです。
確かに、元気いっぱい遊んでいる子どもは子どもらしいです。
しかし、子どもらしさとは、その限りではありません。
十人十色、「子どもらしさ」は「その子らしさ」と言った方が妥当であり、
そもそも、「子どもらしさとは〇〇である」と定義できるものではないのです。
しかし、我が子がもじもじしていたり、
初めての環境に慣れるのに時間がかかり、
なかなか自分を表現できなかったりすると、
親はイライラしてしまいます…。
特に、お教室でそんな姿を見せつけられてしまうと、
怒りがおさまらなくなってしまいます…。
この怒りが、厄介なのです。。。

「もじもじしないで、自分の意見を言いなさい」

「ほら、みんな元気に遊んでいるじゃない」
などと言ってしまうのは
望ましい状況に向かうためには逆効果。
子どもの心まで深く傷つけてしまうということを
まずは改めて意識しなければいけません。

親の言葉で子どもは異なる景色を見るようになります。
励まされて「これから」が見えるようになることもあれば、
否定をされて自己評価を著しく下げてしまうこともあるのです。
親の言葉は宝物にもなりますし、
凶器ともなってしまうということです。
ここは親の踏ん張りどころとも言えるでしょう。
子どもを励ます関わり方:3つの角度からの提案

では、「新しい環境に慣れるのに時間がかかる」事実に対して、
どう向き合っていけばいいのでしょう。
もちろん、子どもが自分でOKと思える時が来れば、
「大丈夫」になるのでしょうが、
もう少し早く自分にOKを出してもらいたい!
周囲を観察するのも良いけれども、
せっかく幼児教室に来ているの!
観察ばかりでなく、実際に動いて経験をしてもらいたい!
こんな気持ちも分かります。
ここでは、子どもが自分にOKを出せるようになるためには
どのような関わり方が良いのか、
「子どもを励ます言葉かけ」を3つの角度からご紹介したいと思います。
1 子ども目線で感じてみる
子どもへの言葉かけで、最も意識したいのは、
「子どもにはどう伝わっているか(どう聞こえているか)」
ということ。
子ども(相手)目線で感じてみるということです。
皆さんが励ますつもりで放った
「もじもじしないで、自分の意見を言いなさい」は、
「あなたは、なんで自分の言いたいことが言えないの」という否定、
「本当に情けない子ね」という見放し、
このような意味合いでお子さんに伝わっているのではないでしょうか。
これでは、更に自分を開放することが難しくなってしまいます。
負のスパイラルですね。

ここで考えるべきことが
相手に伝えたい本当のメッセージです。
「安心して大丈夫だよ」なら、
「お母さんと一緒にやってみようか」になりますし、
「みんなと遊んだら楽しいよ」なら、
「みんな何をして遊んでいるんだろうね、一緒にみてみようか」になります。
不安になっている子どもの気持ちを慮り
「一緒に」と誘っていくことがおすすめです。
焦って子どもを動かそうとするのは、良い結果にはなりません。
2 強みを見つけて伝える
親が「その子らしさ」を見ている環境にある子どもは
安心して「自分」でいることができるため、
そして、自信をもって「自分を表現」できるため、
自己肯定感が高く、意欲的であるように感じます。
子どもを励ますには、
「あなたらしいね」がとても効果的。

褒め言葉というと、
「すごいね〜」
「さすが、〇〇ちゃん!」等、よく使われると思いますが、
それ以上に励まされるのが
「〇〇ちゃんらしいね」という言葉。
お子さんの強みとかけ合わせて
「〇〇ちゃんはここが得意だね」
と伝えてあげれば、
更に子どもは自信をつけていくはずです。
親の目は、どうしても子どもに近づきすぎてしまい、
直すところばかりが見えてしまいます。
だからこそ意識をして、
「その子らしさ」を伝えていただければと思います。
また、自分らしさを知るとは
多様性を知るということでもあります。
みんな違って、だから素敵!
このような感覚を育てることができれば、
新しい環境への緊張感も低くなるのではないでしょうか。
3 手を握るのではなく、手を握らせる

3点目は、子どものペースを大切にするということ。
子どもと手を繋ぐとき、
「皆さんが」お子さんの手を握っていますか?
それとも、「お子さんに」皆さんの手を握らせていますか?
両者には大きな違いがあります。
皆さんが子どもの手を握っている状態では、
子どもが自分にGOサインを出せた
瞬時のタイミングを逃してしまいます。
「楽しそうだ、いってみようかな」というタイミングがあっても、
しっかりと自分の手が握られていれば、
動くこと、できませんよね。
逆に、子どもに自分の手を握らせておけば、
不安な時はずっと握っているでしょうし、
ふと、「大丈夫かも、行ってみよう」と思った時には、
自分から手を離して、外の世界に出ていくことができます。
ちょっと手を離してみて、不安なら
また手を繋ぎにくればいいのですから…。

いつでも帰る場所があること、
それでいて、いつでも安心して外に出ることができるということ。
これが子どもを励ますという観点では
とても重要なことなのです。
「子どもの手を握るのではなく、
子どもに手を握らせる
是非一度試してみてくださいね。
子どもの心の動きが手に表れる様を
きっと体感することができると思います。

「子どもにはこうなって欲しい」
子育てには様々な願いがあることでしょう。
ただし、子どもを無理やり動かすことはできません。
親にできるのは「環境づくり」のみ。
でも、その環境こそが
子どもの将来を変えていくのです。
2歳、3歳という人生の基盤ができる時期だからこそ、
広い視野をもって、豊かな育ちの環境を作っていってくださいね。