「一体いつまで、イヤイヤ期が続くんだろう」。
反抗ばかりしてくる子どもに、こんな気持ちになったことはありませんか?
しかし、子どもの反抗的な態度を、子どもの発達や性質と結びつけてしまうのは、少し乱暴かもしれません。
子どもの態度は、周囲からの言葉かけによって変わります。
例えば、ずっと待っていた順番がやっと回ってきたから、楽しくおもちゃで遊んでいたのに、「順番に使わないとだめでしょう」と言われてしまったら。
今、お風呂に入ろうと思っていたのに、「ぐずぐずしないで早く入りなさい!」と言われてしまったら。
きっと、子どもでなくても悲しい気持ちになってしまいますよね。
そんな時に、まだ言葉で表現することが十分でない幼児は、きっと「反抗」という態度に出てしまのでしょう。
こういった状況を招く背景には、親の「決めつけ」があるものです。
ついついやってしまう、勝手な「決めつけ」について、理解を深めていきましょう。
決めつけ言葉が表れる背景
私たちは、何かを見たり聞いたりした時に、咄嗟に「〇〇に違いない」「〇〇すべき」等、思い込んでしまいます。一つの事実に対して、自分なりの解釈を付しているということ。
そしてその解釈は、「決めつけ言葉」として、相手に届けられることもあります。
◎靴を履くのに手間取っている子どもを見たら
⇒出かけたくなくてグズグズしているに違いない
なんでも人に頼ろうとしているに決まっている
⇒⇒「グズグズしていないで、早く履きなさい!」
◎保育園の帰りにもっと遊びたいと言う子どもに対して
⇒今日は不機嫌に違いない
私を困らせようとしているに決まっている
⇒⇒「わがままばかり言わないの!」
こんな風に、子どもに対してついつい言ってしまうネガティブな言葉の背景には、事実に対する自分の思い込みがあり、それが咄嗟に「決めつけ言葉」として表出されてしまうというわけです。
確かに、これまでに何度も、靴を履くのを嫌がり、グズグズしていた経験があったのかもしれません。保育園の帰りに、遊びたくもないのに「遊ぶんだ。帰らない」と駄々をこねた経験があったのかもしれません。
しかし、たとえ過去がそうであったとしても、今日の子どもも「今までと同じに決まっている」と決めつけてしまうのは、考えもの。子どもの気持ちはその時々で違うから。
そして、子どもは日々ぐんぐんと成長しているからです。ほんの数分の時間をとって、子どもの「今の気持ち」を聞いてあげれば、その後の流れは変わるかもしれません。
「決めつけ言葉」の危険性
親の言葉は、子どもに大きな影響を与えます。
「順番を守れない」と決めつけられれば、「そうじゃない」と反抗的な態度が出てきます。
「ありがとうね、助かるわ」と言われれば、「もっといいことをしよう」と能動的な態度が引き出されます。
発した言葉が、相手の行動を引き出すということです。
また、言われた言葉に反応して、「自分はそういう子どもなんだ」と、自分に対する捉えができてしまうこともあります。「自分は悪い子だ」と自分に対してネガティブな思いを持ってしまったり、自分の本当の気持ちを表現できなくなってしまったり…。
これらは、二次的被害というもので、絶対に避けなければいけません。
状況に対して、「こうに違いない」と思い込んでしまうのは、私たち人間の生理的反応のようなもの。
だからこそ、「自分の決めつけで言葉を発していないか」と振り返っていく姿勢が大切です。
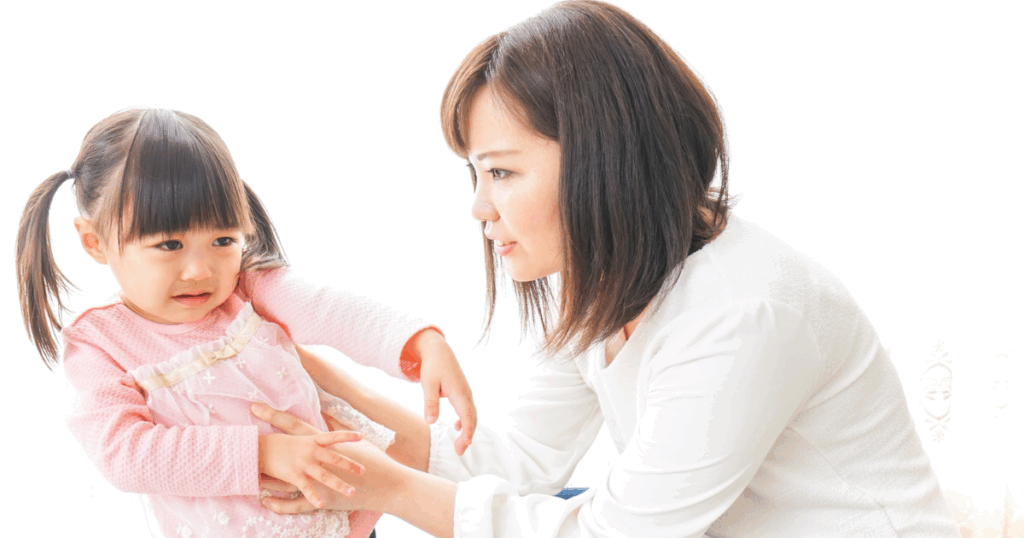
子どもの本当の気持ちを知るための工夫
子どもの態度は、親の言葉かけによって変わります。
しかし、そこには「こういう言葉を言えば、こう言う態度になる」という、二分法的な考え方は当てはまりません。
できるだけ「決めつけ言葉」を排除すること、そして、子どもの本心を知ろうとすること。
親側のこういった心持ちが、子どもに伝えたいことを伝え、子どもからも言いたいことを引き出すために役立ちます。
子どもの本当の気持ちを知るための、3つの工夫をご紹介します。
①傾聴する
子どもの現状に不満があると、どうしても、言葉数が多くなってしまいます。
しかし、子どもの気持ちを知るためには、「話す」より「聴く」。心を傾けて、子どもの言わんとしていることを聴く「傾聴」を意識しましょう。
「この子は何を言いたいのだろう」と、推測しながら耳を傾けます。
アイコンタクト、相槌、うなづき、オウム返しを意識すれば、子どもは心の内を語ってくれるようになるかもしれません。
「そうか、悲しい気持ちだったんだね」「なるほど、今日は疲れてしまったんだね」と、気持ちの代弁をしながら聴いていくと、さらに子どもの心は緩み、本当の気持ちに近づくことができそうです。
②質問する
現代社会には、たくさんのストレスがあります。
慌ただしい子育ての日々、心の中はいつも混雑、頭の中も渋滞状態です。
そんな時には、子どもとの対話をゆっくり楽しめる余裕がないかもしれません。
「質問」を意図的に利用しましょう。
共感的に寄り添った上で、質問を投げかけると、短時間でも深いコミュニケーションが取れるようになります。
「そうか、わかってもらえなかったんだね。本当はどうしたかったのかな?」
「もっと遊びたいよね。あと5分間だけ遊べるよ。一番したいことは何かな?」
ただ、ここで意識をしなければならないことがあります。
それは、子どもからの返答は「必ず一旦は受け止める」ということ。
もしかすると親の意に反する返答が返ってくるかもしれませんが、そこで否定するのはNGです。
「そうなんだね」と、一旦は子どもの気持ちを受け入れ、その後自分の意見を伝えるのがオススメです。
③観察する
子どもは、すべてを語りません。
特に幼児は、心の内を十分に表現する言葉を持ち合わせていませんので、本心を言語にすることができなかったりします。
「観察」を意識しましょう。
子どもの表情や態度を観察し、言葉にならない声を探ります。
「話したくない」ということもあるでしょう。
そんな時には、無理に言葉にさせようとせず、ただ隣に座って同じ景色を見るだけでも十分です。
焦らずゆっくり、子どものペースを大切に。
観察するプロセスは、子どものことを「知ろうとする」プロセスでもあります。
大好きな親御さんが、自分に興味を持ち、わかろうとしてくれている様子に、子どもは安心感を覚えるはずです。
決めつけは誰にでも起きうること。
だからこそ、自覚することが大切です。
「勝手な決めつけ言葉」が、乱暴に子どもにぶつけていないか、時に振り返ってみてくださいね。

体験授業受付中♪♪
クロワール幼児教室では随時体験教室を受け付けております。
まずはお気軽にご連絡下さい。以下のバナーをクリックして詳細ご確認ください。

記事執筆
江藤真規
https://saita-coordination.com/
親も一緒に育っていく2歳からの学びの場
クロワール幼児教室
https://croire-youjikyousitu.com/




