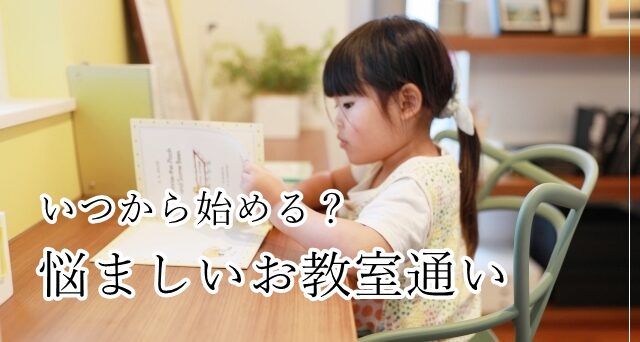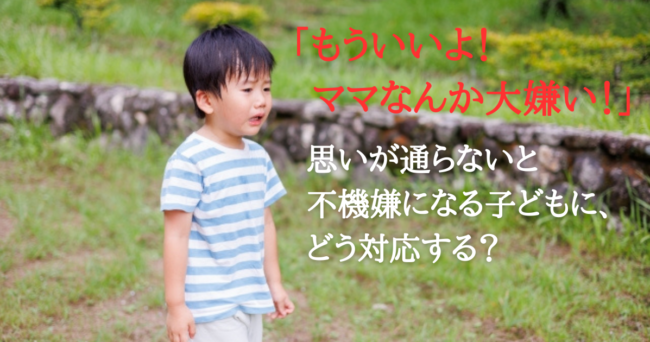東京・四谷にありますクロワール幼児教室です。成長が著しい2歳・3歳の時期を丁寧にサポート、非認知能力を重視した上で、小学校・幼稚園受験の基盤づくりも行っています。
調子よく進めてきたプリント学習なのに、このところ嫌がるようになってきた。
子どものやる気には、浮き沈みがありますので、こんなこともあるでしょう。
それでも、毎日決まった量をこなす必要がある時には、ついついご褒美に頼ってしまいます。
「終わったら〇〇をしていいから頑張って!」といった具合です。
しかし、これが加速してしまうと、子どもはプリント学習を行う前に、ご褒美を要求してくるようにも。
そのうち「〇〇していいなら、プリントをやってあげる」と、
まるで親のためにやってくれているような状況にさえ…。
これではいけないと思いつつも、受験のために「やらなければならない勉強」が目の前にある以上、
「なら、やらなくていい!」とも言い切れず、複雑な気持ちになってしまいます。
子どもの勉強と向き合う際に意識したいことについて、考えてみましょう。
わがままを増やす親の「応じすぎ」
「〇〇ちゃんはどっちがいい?」「やりたい?やりたくない?」。
子どもの気持ちを尊重した子育てを大切にしているご家庭には、こんなやりとりが多いはず。
子どもの主体性を育てるためには、「子どもの意見を聞く」のは、とても大切です。
しかし、このやりとりは、時に難しさが出てきてしまいます。
例えば、勉強等の決まった課題をこなさなければいけなくなった時。
「どうしたい?」「やりたくない」への返答に困ってしまいます。
やらねばならないことがある場合には、「やりたくない」を通すわけにはいかず、
上述の「ご褒美」が出てきてしまいます。
ご褒美は、子どもの動機付けになるので、決して悪いことではないのですが、過度なご褒美になるのは要注意。
子どもの中で、「言えば応じてもらえる」という誤解が膨らみ、「応じてくれない」場合に、
感情を爆発させてしまうからです。
わがままが過ぎるという状況です

義務感より得意意識
確かに、受験等を控えている場合には、「やらねばならない」ことがたくさんあります。
ただ、親の目には「やらねばならないこと」であっても、子どもにとっては「義務感」とならないよう、
工夫をしていくことが大切です。
幼児は楽しいからやるのです。
面白いから没頭するのです。
5歳にもなると、口では「あ〜、やらなきゃいけないんだよね〜」と言うことも出てきますが、
それでも子どもは、面白くなければ動きません。
義務感で勉強をやらせているうちは、あまり身についていないということです。
「(やりたくないだろうけど)これを頑張ったらご褒美」と義務感を植え付けるより、得意意識を育てましょう。
「早くできるようになったね」「さすが、5歳は違う」「あれ、もうこんな難しいことをやっているの?」等、
子どもへの言葉かけの工夫で、得意意識は育ちます。
勉強は楽しいことという前提で、「お父さんも一緒にやりたいな〜」「お母さんにもできるかな」もいいでしょう。
人に教える経験は、深い学びにつながります。
「お父さんにも教えてくれる?」と、先生役に仕立てるのもおすすめです

わがままへの3つの対処
子どもは経験から学んでいくため、すでに子どもの中に「嫌だと言えば親が応じてくれる」
という考え方ができてしまっている場合もあるでしょう。
わがままへの対処、3つの方法について解説します。
□「No」と言う勇気を持つ
ダメなことはダメ。
「No」という勇気を持ちましょう。
親の応答が突然変わると子どもは混乱するかもしれません。
それでも、悪しき習慣を継続していくより、ここから新たな習慣をつくる気持ちで、毅然とした態度で接します。
ただ、その際にはダメな理由を説明することを忘れずに。
なぜ、ダメなのか。
その理由を子どもが理解できるまで、丁寧に粘り強く伝えます。
時間がかかるかもしれませんが、きっと子どもには伝わります。
そして、子どもの行動が改善された際には、大いにほめてあげましょう。
わがままをエスカレートさせ、親子の関係がギクシャクしてしまうより、圧倒的に良い未来が築けるはずです。
□わかりやすいルールを作る
4、5歳にもなれば、子どもはルールがあることを理解するようになります。
そしてルールがあるからこそ、もっと楽しく遊べることも認識していきます。
子どもの願い(わがまま)が通らないことを示す際に、ルールで示すと伝わりやすくなります。
例えば、YouTubeを観るのは1日30分までというルール。
「もっと観たい」となった時には、「残念だけど、ルールなんだ」と伝えます。
「約束したでしょ」や「ダメって言っているでしょ」と、子どもを否定するより、
子どもの納得感が増すとともに、親子関係にもネガティブな影響を与えません。
もちろん、ルール通りにできた時には「ルールを守れたね」と褒めてあげます。

□感情的に反応しない
子どものわがままに対応する際には、親の冷静さが必要です。
深呼吸をして自分の心を冷静にしてから対応する、子どもが落ち着くのを待ってから対応する等、工夫が必要です。
受験に向けて、気持ちがいっぱいいっぱいになっている時には、誰かに心の内を聞いてもらいましょう。
モヤモヤを吐き出すことで、気持ちに余裕が生まれます。
また、自分がなぜ感情的になっているか、その理由を探してみるのも、心に余裕を持つためには効果的。
「私は今、なぜこんなに怒っているのだろう」と自問自答をしてみます。
「時間に追われているから」等、理由が見えてくれば、対処法も見つかりそうです。
好きという気持ちは、大きな力になります。
そして、子どもは面白いことが大好きです。
勉強であっても、スポーツであっても、入り口には「面白さ」を備え、好きという気持ちを育てていきましょう。「好きになったもの勝ち」です。

記事執筆
江藤真規
https://saita-coordination.com/
親も一緒に育っていく2歳からの学びの場
クロワール幼児教室
https://croire-youjikyousitu.com/
体験授業受付中